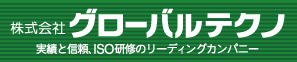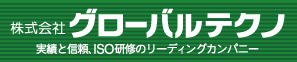|
マネジメントシステム認証懇談会、「MS信頼性ガイドラインに対するアクションプラン -Part 2-」を発表。(2011.1.7) |
 |
| |
マネジメントシステム認証懇談会は、「MS信頼性ガイドラインに対するアクションプラン -Part 2-」を発表した。本報告書は、2009年8月に策定された「アクションプラン -Part 1-」の実行状況と、新たに策定された追加アクションプランをまとめたもの。
このアクションプランはまず、2008年7月29日に経済産業省より公表された「マネジメントシステム規格認証制度の信頼性確保のためのガイドライン」に対応するため、日本適合性認定協会(JAB)、日本情報処理開発協会(JIPDEC)、日本マネジメントシステム認証機関協議会(JACB)を主なメンバーとする、“マネジメントシステム信頼性ガイドライン対応委員会”が検討、その成果を2009年8月に「アクションプラン -Part 1-」として公表。今回は、さらに要員認証機関も加え、“マネジメントシステム認証懇談会”として再編し、検討されたものです。
・MS信頼性ガイドラインに対するアクションプラン -Part 2- (マネジメントシステム認証懇談会報告)
|
 |
 |
 |
 |
国土交通省、「経営事項審査の審査基準の改正等について」発表。
ISO9001及びISO14001の取得が経審の評価項目に追加(2010.11.16)
|
 |
| |
国土交通省 総合政策局建設業課は、「経営事項審査の審査基準の改正等について」を発表した。公共工事を受注しようとする建設業者の経営を評価する経営事項審査制度について、従来にも増して適正に評価できる仕組みに改善していくため、中央建設業審議会において検討を行ってきた。今回、社会経済情勢を踏まえた多様なニーズへの対応の観点から改正を行ったとのこと。ISO9001及びISO14001の取得が経審の評価項目に追加された(片方で5点、両方で10点)。詳しくは下記参照。
・国土交通省 総合政策局建設業課 「経営事項審査の審査基準の改正等について」 |
 |
 |
 |
 |
世界のマネジメントシステム認証件数、2009年版発表(2010.10.28) |
 |
| |
世界のマネジメントシステム認証件数(ISO Survey-2009)が、ISO中央事務局より公表された。各規格の認証件数上位国は表のとおり。
|
|
ISO 14001
(環境) |
ISO/TS16949
(自動車産業) |
ISO/IEC27001
(情報) |
ISO 22000
(食品安全) |
ISO 13485
(医療機器)
|
1
|
中国
257,076件 |
中国
55,316件 |
中国
12,071件 |
日本
5,508件
|
中国
3,342件 |
ドイツ
3,019件 |
2 |
イタリア
130,066件 |
日本
39,556件 |
アメリカ
3,882件 |
インド
1,240件 |
トルコ
1,134件 |
アメリカ
2,834件 |
3 |
日本
68,484件 |
スペイン
16,527件 |
韓国
3,857件 |
イギリス
946件 |
ギリシャ
987件 |
中国
1,498件 |
4 |
スペイン
59,576件 |
イタリア
14,542件 |
ドイツ
3,205件 |
中華台北
934件 |
インド
948件 |
イギリス
1,330件 |
5 |
ロシア
53,152件 |
イギリス
10,912件 |
インド
2,660件 |
スペイン
483件 |
中華台北
810件 |
イタリア
1,109件 |
6 |
ドイツ
47,156件
|
韓国
7,843件 |
日本
1,195件 |
中国
459件 |
ルーマニア
661件 |
スウェーデン
836件 |
7 |
イギリス
41,193件 |
ルーマニア
6,863件 |
フランス
1,096件 |
ルーマニア
303件 |
ポーランド
549件 |
フランス
788件 |
8 |
インド
37,493件 |
ドイツ
5,865件 |
ブラジル
1,077件 |
イタリア
297件 |
スリランカ
329件 |
カナダ
453件 |
9 |
アメリカ
28,935件 |
アメリカ
5,225件 |
イタリア
1,070件 |
チェコ
264件 |
スペイン
269件 |
日本
452件 |
10 |
韓国
23,400件 |
チェコ
4,684件 |
メキシコ
990件 |
ドイツ
253件 |
キプロス
245件 |
中華台北
362件 |
なお、増加件数が多いのは、ISO 9001では、1位 ロシア、2位 中国、3位 イタリア。
ISO 14001では、1位 中国、2位 日本、3位 ルーマニアとなっている。
詳しくは、ISOのホームページ(http://www.iso.org/iso/survey2009.pdf)をご覧ください。 |
 |
 |
 |
 |
ISO/TC176/SC2、ISO9000ファミリーに関するユーザ調査開始(2010.10.26) |
 |
| |
ISO/TC176(品質保証及び品質管理)/SC2(品質システム)では、ISO 9001(品質マネジメントシステム−要求事項)の次期改正について検討中。この度、ISO 9001をより使い易く、有効なものとするために、ISO 9001を中心としたISO 9000ファミリー規格に関し、利用者の方々から幅広くユーザ調査を実施している。本調査は、ISO/TC176における今後の規格の改正などの参考となる重要な調査となり、どなたでも参加いただけるとのこと。オンラインで回答いただく形式で、日本語での回答が可能。
詳しくはこちらから(http://www.jsa.or.jp/stdz/iso/iso9000.asp#4)。 |
 |
 |
 |
 |
2015年改訂時におけるQMS、EMS等の共通テキスト部分の概要が少しずつ明らかに!(2010.10.14) |
 |
| |
ISO 9001、ISO 14001の改訂が当初予定の2012年から2015年に延びた背景には、2006年にISOマネジメントシステムの共通部分を整合化した要求事項にするというISO/TMB(技術管理評議会)の考え方が影響しているのはご存知のとおりである。その焦点となる共通部分のテキストの概要が、本年7月に開催されたISO/TC207レオン総会でかなり明確になった。
現在、この共通部分のテキストの開発はTMB/JTCG(合同技術調整グループ)が担当しているが、同グループが2008年に共同ビジョンを採択し、「すべてのISOマネジメントシステムの要求事項規格は共通部分の目次構成と要求内容及び用語の定義を共有し、個々の適用分野で特有の必要性がある場合に限って相違が認められる」ことを宣言し、2009年9月には以下の共通目次構成で概ね合意がなされている。つまりISOが目指す次世代のマネジメントシステムとは、共通要素の上にQMSやEMS等の分野ごとの固有の要求事項を乗せた構成になるわけである。
ISOマネジメントシステム規格の共通目次案
序文
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 組織の状況
4.1 組織とその状況の理解
4.2 ニーズと要求事項
4.3 マネジメントシステムの適用範囲
5 リーダーシップ
5.1 経営者のコミットメント
5.2 方針
5.3 組織での役割、責任及び権限
6 計画
6.1 目的とその達成計画
7 支援
7.1 資源
|
7.2 力量
7.3 認識
7.4 コミュニケーション
7.5 データの管理
8 運用
8.1 運用計画
8.2 不適合の管理
9 パフォーマンス評価
9.1 監視及び測定
9.2 内部監査
9.3 分析と評価
9.4 マネジメントレビュー
10 改善
10.1 是正処置
10.2 予防処置
10.3 継続的改善
|
この中の4〜10の7つの章立てを「高次構造」と称して、マネジメントシステムの基本構造としている。また「組織の状況」とは組織が特定の分野でマネジメントシステムを実施するにあたって、組織内外の関連状況を把握するプロセスのことで、ISO 9001では顧客要求事項の把握や製品安全等、製品に要求される法的要求事項等を特定するプロセスにあたる。またISO 14001 では環境側面の把握と著しい環境側面の特定、法的及びその他の要求事項の特定などのプロセスがこれに相当する。これはいかなるマネジメント領域でも必ず状況認識のプロセスが存在するという前提に立った構成、考え方である。「リーダーシップ」は経営層のリーダーシップの重要性から独立させ、続く「計画」、「運用」、「パフォーマンス評価」、「改善」という章立てがそれぞれのPDCAに該当し、「支援」はPDCAの動作を支援する要素群を集めたものになっている。
JTCGでは2012年5月を目標に共通部分の開発を完了させる計画であるが、QMS、EMSの2015年改訂時期を踏まえれば、2011年初頭から共通テキストのDIS(国際規格案)が発行され、内容が逐次判明してくるものと思われる。(注:参考資料「環境管理」Vol.46、No.3「ISO14001改訂に向けたISO での動向」(吉田敬史氏))(グローバル・ニュース No.10より) |
 |
 |
 |
 |
第27回ISO/TC176(品質管理)ボゴタ総会の概要(2010.10.14) |
 |
| |
ISO/TC176の第27回総会が2010年6月7日〜12日、南米コロンビアのボゴタで開催され、35ヵ国、12機関、200名が参加して(日本からは8名)開催された。総会の概要は以下のような内容。
1. TC176戦略計画
2009年の東京総会で戦略計画タスクフォースが設置され、その第2次案を作成した。要点は以下の内容。
・ ISO 9000ファミリーが今後も持続的に発展していくために、ISO 9001を中心としたISO 9000 ファミリーと社会との相互関係を「ISO 9000エコシステム」として捉える。 ・ 製品、プロセス、人々、利害関係者の側面から戦略目標を定める。
2. SC1(ISO 9000:基本及び用語)
・ 2005 年以降に発行されたISO 9001/9004などの規格を盛り込んだ用語規格として改訂予定。 ・ SC2との合同TGを設置し、現在の8つの品質マネジメントの原則を再度見直し、追加すべき要素及びISO 9001で求められるレベル等を検討することを決定。
3. SC2(ISO 9001:要求事項、ISO 9004:持続的成功の指針)
・ 次期ISO 9001は2010年12月までにSC2戦略計画の第1次案(コメント)、2011年4月までに第2次案(投票)を作成し、2011年中頃DS(規格の設計仕様書)の作成、2012年中頃から起草(3年)を経て2015年発行の見込み。 ・ Future9001 TGで、将来のISO 9001で対応すべき20のコンセプトを3つの主要カテゴリーに分類。それぞれのコンセプトに対し、コンセプトの説明、現在の適用状況、今後の適用及び影響などを検討。 ・ ISO 9004の支援文書をレビュー、トップマネジメント向け小冊子を含め、2010年中には公開予定。 ・ ISO 9001の中小企業向けのハンドブック(中小企業のためのISO 9001)を6月8日に発行。 ・次回SC2会議は2010年11月〜12月に開催予定。
4. SC3(支援技法)
・ ISO/TS 10004(顧客満足の監視・測定)はIS(国際規格)に格上げするための作業を実施したが、手続き上の問題点を指摘され、ISO 10001/2/3(顧客満足シリーズ)との整合性確保に焦点をあて、明確にするためのマイナーチェンジを行い、スコープの変更はしないことを確認。 ・ ISO 19011(マネジメントシステム監査)は、今回の総会で会議の開催はしていない。2010年12月のシドニー会議を経て2011年中頃IS発行見込み。 ・ ISO 10008(電子商取引)は序文、適用範囲、定義、原則部分を作成。2013年にISを発行予定。 ・ CASCO(適合性評価委員会)では、ISO/IEC 17021-2(マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項並びにマネジメントシステムの第三者認証審査に対する要求事項)に関連した、分野固有の監査員に関する要求事項を作成する予定。
5. 次回TC176総会
2011年10月〜11月に開催予定(場所は未定)。なお、「ボゴタ総会」の概要詳細を知りたい方は、(財)日本規格協会(JSA)のホームページ(http://www.jsa.or.jp/stdz/iso/iso9000.asp) の中の「ISO/TC176関連会議情報」を参照。(グローバル・ニュース No.10より)
|
 |
 |
 |
 |
第17回ISO/TC207(環境管理)レオン総会の概要―ISO 14001次期改訂議論がスタート―(2010.10.14) |
 |
| |
第17回ISO/TC207総会が、メキシコ・レオン市で、2010年7月11日(日)〜17日(土)にわたって開催された。総会には39カ国、12機関から約223名の参加があり、日本からもSC1国内委員会委員長である吉田敬史氏を日本団長として、企業、大学、関係省庁、標準化関連機関などから25名が出席した。
本総会の主なトピックスは、次期ISO 14001改訂の議論である。SC1では、2009年のTC207カイロ総会においてfuture challenge for EMS Study Group(以下、future EMS SG)を設置し、次期ISO 14001改訂において考慮するべき事項として11項目をあげ検討を開始した。レオン会合では、各々のテーマに対しての現状分析とISO 14001改訂に関する推奨事項を検討し、次期改訂へのインプットとして最終文書を作成した。11項目は次のとおり。
1)サステイナビリティ及び社会責任 2)環境パフォーマンスの改善 3)法令規制への順守 4)ビジネスマネジメント 5)適合性評価 6)小組織における実施 7)バリューチェーン/サプライチェーンにおける環境影響 8)ステークホルダーエンゲージメント 9)GHG、エネルギー使用等との併用 10)外部コミュニケーション(製品情報を含む) 11)国家/国家間の方針における位置づけ
次期ISO 14001改訂に関するスケジュールは、SC1内にISO 14001改訂のアドホックグループ(AHG)を設置し、future EMS SGの報告をインプットとして、ISO
14001の妥当性評価、デザインスペック及び新業務項目提案(NWIP)の内容を準備し、2011年4月までに作業を終了し、SC1に作成文書を提出するという。その他の動向としては、新規格のISO 14046(ウォーターフットプリント)が10月にWD2回付、ISO 14067(カーボンフットプリント)がCD2へ移行、ISO 14066(GHG検証/妥当性評価者への力量要求事項)がDISからFDISへ移行することが決定した。また、日本提案のISO 14051(マテリアルフローコスト会計)は、現在DIS投票中である。(グローバル・ニュース No.10より) |
 |
 |
 |
 |
ISO 9004:2009がJIS Q 9004:2010として10月に発行―他の規格の開発・発行状況の動向も―(2010.10.14) |
 |
| |
既報のとおり、昨年11月に発行されたもののJIS化が遅れていたISO 9004(組織の持続的成功のための運営管理―品質マネジメントアプローチ)が10月20日の官報公示後JIS Q 9004:2010として(財)日本規格協会から発行されることが決定した。現時点では正式な発行日及び価格は不明であるが、慣例に従えば10月21日発行になる。また、ISO 19011(マネジメントシステム監査のための指針)は現在DIS(国際規格案)の5ヵ月投票中で、2011年にはIS(国際規格)として発行の予定。
この規格と関連するISO 17021-2(適合性評価―マネジメントシステムの第三者審査に対する要求事項)は、すでに「パート2」という言い方を中止し、ISO 17021の中に取り込まれ追加要求事項として開発中であるが、ISO 17021自体の開発状況は、9月21日時点でFDIS(最終国際規格案)投票(2ヵ月)の段階なので、本年12月末にはISとして発行される模様だ。最後になるが、以下の4規格がJIS化され9月21日より販売が開始されている。
(1)JIS Q 0073:2010(リスクマネジメント―用語)定価1,680円(和文冊子価格、以下同一)。(2)JIS Q 10001:2010(品質マネジメント―顧客満足―組織における行動規範のための指針)定価1,890円。(3)JIS Q 10003:2010(品質マネジメント―顧客満足―組織の外部における紛争解決のための指針)定価2,625円。(4)JIS Q 31000:2010(リスクマネジメント―原則及び指針)定価2,625円。(グローバル・ニュース No.10より) |
 |
 |
 |
 |
ISO 14005、FDIS投票開始(2010.10.14) |
 |
| |
小企業を対象とした環境マネジメントシステムの段階的適用の指針であるISO 14005がFDIS(最終国際規格案)段階を迎え、10月26日を締切りとして投票が行われている。策定段階では紆余曲折のあった同規格も2010年内の発行に向けて最終段階に入ったが、一部の国を中心とした反対意見も未だ根強く、今後の展開から目の離せない状況が続いている。
同規格は、主に中小規模の組織がISO 14001を段階的に導入するための指針であり、3段階と5段階のステップに分けて組織の必要性と資源に合わせて環境マネジメントシステムを構築し、最終的にはISO 14001と同レベルへの到達を目指す仕組みとなっている。国内ではISO 14005を利用した認証サービスをいくつかの認証機関が開始する予定だが、同規格は英国のAcornスキーム(ISO 14001及びEMASの段階的認証制度)の認証基準であるBS 8555がベースとなっているため、同様の形式での認証サービスは可能といえる。なお、日本適合性認定協会(JAB)としては現在のところ認定プログラムの計画はないようだ。(グローバル・ニュース No.10より) |
 |
 |
 |
 |
JIPDECが「個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン-第2版-」を公表(2010.10.14) |
 |
| |
プライバシーマーク制度運営団体であるJIPDEC((財日本情報処理開発協会)は9月、2006 年版JISに対応した個人情報保護マネジメントシステム構築と運用の指針となるガイドライン第2版を作成し、公開した。この第2版は、2007年にJISの各要求事項に対する審査の視点、個人情報保護マネジメントシステム構築の手順、留意事項をまとめた第1 版を発行していたが、この度新たに「審査の着眼点」を取り込み、要求事項・審査項目ごとの見方を詳しく解説しているのが特徴。
「JIS Q 15001:2006をベースにした個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン―第2版―」はJIPDECのホームページ(http://privacymark.jp/news/2010/index.html)に掲載されている。また、(財)日本規格協会からもJIS要求事項を掲載した同名の書籍(最新の法規・各省庁のガイドライン付)を定価2,625円(税込)で販売している。(グローバル・ニュース No.10より)
|
 |
 |
 |
 |
大日本スクリーン製造(株)が、世界初ISO/DIS 50001認証取得(2010.10.14) |
 |
| |
大日本スクリーン製造(株)は、2010年7月27日、現在制定作業が進んでいるエネルギーマネジメントシステム規格「ISO 50001」国際規格案(Draft International Standard:DIS)の認証を世界で初めて取得した。ISO 50001は、企業などが利用・排出するエネルギーの総合的な管理を目的に開発されたマネジメントシステム規格で2011年に発行が予定されている。
同社は今回、経済産業省が定めるエネルギー管理指定工場である洛西事業所において認証を取得。また同時に欧州版エネルギーマネジメントシステム「BS EN16001」の認証も取得している。今後は、国内の主要事業所を対象として、さらに認証の取得を進め、今年度のCO2排出量を生産量に対して1%以上、エネルギーコストを5%以上削減することを目標に掲げ、コーポレートガバナンスの一環として実践するとともに、社会環境への貢献に努めていくという。同社は、品質管理や環境マネジメントシステムの整備に早くから取り組み、各事業所、グループ会社へと対象を拡大。そして2009年10月には、同社グループとして環境マネジメントシステムを統合した。さらに今後、労働安全衛生マネジメントシステム(OHSAS 18001)との統合も予定しているという。(グローバル・ニュース No.10より) |
 |
 |
 |
 |
ISO 14040/ISO 14044のJIS化が決定(2010.10.14) |
 |
| |
ライフサイクルアセスメント(LCA)規格であるISO
14040(原則及び枠組み)及びISO 14044(要求事項及び指針)のJIS化が承認され、2010年10月発行の見込みとなった。ISOのLCA規格は、1997年のISO 14040発行を皮切りにISO 14041(インベントリ分析)、ISO 14042(ライフサイクル影響評価)、ISO 14043(ライフサイクル解釈)といった技術的内容ごとに策定・発行されてきた。そのため規格の読みやすさを向上させることを目的に、上記規格をISO 14040とISO 14044に統合し新規格として2006年に発行していた。
国内ではJIS化されていなかったが、CO2排出量の検証など、LCA手法がGHGマネジメントのベースとして活用されていることから、早期のJIS化が期待されていた。なお、ISO 14040及びISO 14044は2009年に定期見直しが実施され、今回のレオン総会にて「確認(改訂なし)」との見直し結果が承認されている。また、来年の総会では今後の改訂の必要性について検討が開始されるという。(グローバル・ニュース No.10より) |
 |
 |
 |
 |
ISO 26000(社会的責任)、11月1日にISとして発行(2010.10.14) |
 |
| |
既報のとおり、ISO 26000(ISO/SR、社会的責任規格)が7月12日からFDIS(最終国際規格案)。として2ヵ月間回付されていたが、9月14日に承認され、当初予定の本年12月から11月1日に早められてIS(国際規格)として発行されることが決定した。
2002年9月のISO/TMBに高等諮問委員会(SAG)を設置してCSRの規格化の検討を開始して以来、2003年2月には名称をCSRからSRに変更、作業文書(WD)も四次2版までかかり、その後2008年12月にCD(委員会原案)回付、2009年9月にDIS(国際規格案)回付、本年7月にFDIS回付と実に8年経過してのIS発行となる。現時点では規格の内容はDIS段階のものしか判明していないが、ISが発行され次第(財)日本規格協会から本規格の説明会が開催されるものと思われる。(グローバル・ニュース No.10より) |
 |
 |
 |
 |
JABが財団法人から公益財団法人に移行、また新理事長に久米均氏が就任(2010.10.14) |
 |
| |
日本における適合性評価制度全般にかかわる民間唯一の認定機関として活動していた(財)日本適合性認定協会(JAB)が、7月1日より公益財団法人日本適合性認定協会に移行し、新たな出発をすることになった。これは2008年12月1日施行された「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」に基づくもの。それに伴い、理事長も8月5日付で金井努氏から久米均氏へと交代した。
ご存知のように、久米氏は(当時・東京大学理工学部教授)1982年1月の(財)日本規格協会 ISO/TC176国内委員会委員長就任を皮切りに、国内ISO関係の要職を歴任し、日本のISO9000 草創期における重鎮ともいえる人物。現在のISOマネジメントシステム全般にかかわる様々な問題点の解決や今後のさらなる発展に対し、認定機関の理事長としてどのような施策をとられるかが大いに注目される。(グローバル・ニュース No.10より)
|
 |
 |
 |
 |
バックナンバーはこちら |
 |
 |
 |