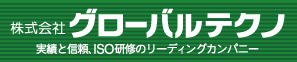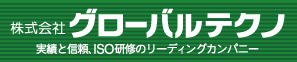|
環境・品質マネジメントシステム審査の力量要求事項「JISQ17021-2」、「JISQ17021-3」発行(2014.2.4) |
 |
| |
2014年1月20日、「環境マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項(JIS Q 17021-2)」及び「品質マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項(JIS Q 17021-3)」が発行されました。
ISO17021(JIS Q 17021)「マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項」では、マネジメントシステムの審査及び認証の質を向上させる目的で、審査及び認証に対する力量に関する要求事項が追加されました。しかし、ISO17021の適用範囲には各種マネジメントシステムが含まれていますが、各々のマネジメントシステムの審査及び認証に求められる力量基準は規定されていません。そこでISO17021を補足する環境・品質マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項として「ISO/TS17021-2」が2012年8月に、「ISO/TS17021-3」が2013年5月に制定されました。
両要求事項ともTS(技術仕様書)として作成されましたが、IAF(国際認定機関フォーラム)において環境・品質マネジメントシステム認証に関わる規準文書として採用されたことへの重要性を考慮し、国内ではJISとして発行されています。
内容は、ISO17021の附属書Aに取り上げられている認証の機能を、審査、申請のレビューの実施、審査報告書のレビュー及び認証の決定の三つとし、個々の審査員または審査チームとして求められる力量及び認証機関の要員に求められる力量を規定しています。今後審査員を目指す方はもちろん、認証組織の方々も今後の環境・品質マネジメントシステム審査員がどのような力量を要求されるのか、参考にご覧いただくことをお奨めします。
〜text by 研修部 澤本 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.34より〜 |
 |
 |
 |
 |
ISO/TC176ポルト総会(2013/11)概要報告〜JSAのホームページ(2014.2.4) |
 |
| |
JSA(一般財団法人日本規格協会)のホームページに、2013年11月4〜9日に、ポルトガルのポルトにて行われた「ISO/TC176(品質管理及び品質保証)総会」の概要報告が掲載されました。ISO9001については、2014年3月にパリで会議を開催し、引き続きDIS作成作業を行う予定。2014年4月のDIS回付を目指すとのこと。詳しくはこちら(http://www.jsa.or.jp/stdz/iso/iso9000.asp#2)をご覧ください。
〜メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.34より〜 |
 |
 |
 |
 |
マネジメントシステム基礎講座/共通テキスト、逐条解説 4 (2014.2.4) |
 |
| |
箇条6は、組織が取り組むべき「リスク及び機会」を決定し、それに対する取り組みを計画するとともに、XXX方針に沿ったXXX目的を設定し、そのXXX目的を達成するための計画を策定することを要求しています(XXXには、「品質」「環境」「情報セキュリティ」などの語が入ります)。
箇条6.1には、共通テキストで新たに加わった「リスク及び機会」という重要なキーワードが出てきますので、少ししつこく解説します。
箇条6 計画
6.1 リスク及び機会への取組み
ここでは、箇条4.1(組織及びその状況の理解)で決定された「組織の内部及び外部の課題」、さらに箇条4.2(利害関係者のニーズ及び期待の理解)で決定された「利害関係者の要求事項」を考慮したうえで、
・XXXマネジメントシステムの意図した成果を達成できること
・望ましくない影響を防止又は低減すること
・(XXXマネジメントシステムの)継続的改善を達成すること
のために、取り組む必要がある「リスク及び機会」を決定することが求められています。
それでは、どのような「リスク及び機会」があるのか? については、そもそも箇条4.1で決定された課題は何か? さらに、箇条4.2で決定された利害関係者の要求事項は何か? に遡らないと説明のしようがないので、ここでは具体例には触れませんが、要するに、箇条6.1の前半では、XXXマネジメントシステムの「意図した成果」と「継続的改善」を達成し「望ましくない影響を防止/低減」するために何らかのかたちで取り組まなければならない「リスクと機会」にはどのようなものがあるか? をひとまず決めなさいということが要求されているわけです。
ところで、「リスク及び機会」という組合せ語は、「ニワトリが先かタマゴが先か」という堂々巡りの議論同様、各方面で喧々諤々の議論が繰り広げられているようです(あくまで筆者の憶測です)。
共通テキストでは、「リスク」とは「不確かさの影響」という大変高尚な定義がされています。この定義の中には「好ましい」「好ましくない」という概念はありません。とはいえ、現代の一般市民にとって「リスク」とは好ましくないものを指すことが多いので、好ましくない不確かさと好ましい不確かさをセットにして「リスクと機会」という意味だと解釈できないこともありません。一方で「好ましいリスク」も「リスク」の中に含まれるのだから、「機会」とはもうちょっと先のチャンスや改善の種やなんやかんやも含まれるのだ!と解釈することもできるでしょう。
この議論を分かりやすいようにあえて数式で表すと次のようになります。
“R(リスク)=Rx「好ましくないリスク」+Ry「好ましいリスク」”
この数式はISOガイド73、ISO31000、共通テキストのいずれの定義とも矛盾はしません。
一方、共通テキストの「リスク及び機会」には次の2通りの解釈があり得ます。
“R1「リスク及び機会」=Rx「好ましくないリスク」+Ry「好ましいリスク」”
機会=Ry「好ましいリスク」と解釈し、「リスク及び機会」はR「リスク」と同義と捉える。
“R2「リスク及び機会」=R「リスク」+K「機会」”
「リスク」(Rx「好ましいリスク」+Ry「好ましくないリスク」)とK「機会」は別物なので、「機会」はRy「好ましいリスク」よりもっと改善よりの概念と捉える。
共通テキストの「リスクと機会」が、“R1=Rx+Ry”と“R2=R+K”のどちらなのか? については、2015年のISO9001/ISO14001改訂までに、識者による公式な表明がなされることを願ってやみません(どちらでもいいって話ではないでしょうから)。
さて共通テキストに戻りますが、箇条6.1の後半では「リスク及び機会」を決定したうえで、組織はさらに「リスク及び機会」への取組みについて計画することが要求されています。またその際、その取組みを「XXXマネジメントシステムプロセスにどのように統合するのか、さらに、その取組みの有効性をどのように評価するかについても計画しなければなりません。
ISO/CD 9001では、箇条6.1は共通テキストとほとんど変わりはありません。ISO/CD 14001では、6.1.2環境側面の特定、6.1.3順守義務の決定、6.1.4著しい環境側面並びに組織リスク及び機会の決定、6.1.5処置を取るための計画策定などの箇条と要求事項が追加されています。ISO/IEC 27001:2013では、6.1.2情報セキュリティリスクアセスメント、6.1.3情報セキュリティリスク対応、の箇条と要求事項がここに追加されています。それぞれのマネジメントシステムが扱うリスクとその扱い方に応じて、リスクの決定・評価・対応に関する要求事項が箇条6.1に追加されていることは大変興味深いですね。
次回は、「箇条6(後半)」について、さらっと解説します。
−補足−
統合版ISO補足指針の附属書(Annex SL)に収録されている「共通テキスト」は、日本規格協会の「マネジメントシステム規格の整合化動向」のwebページ(http://www.jsa.or.jp/stdz/mngment/mngment03.asp)で公開されています。このページの「ISO MSS上位構造、共通テキスト及び共通用語・定義(英和)」をクリックすると、対訳資料を閲覧できます。この連載とあわせて、ぜひ原文もお読みになることをお薦めします。
〜text by 研修部 萬木 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.34より〜 |
 |
 |
 |
 |
マネジメントシステム基礎講座/共通テキスト、逐条解説 3 (2013.12.25) |
 |
| |
−はじめに−
統合版ISO補足指針の附属書(Annex SL)に収録されている「共通テキスト」は、日本規格協会の「マネジメントシステム規格の整合化動向」のwebページ(http://www.jsa.or.jp/stdz/mngment/mngment03.asp)で公開されています。このページの「ISO MSS上位構造、共通テキスト及び共通用語・定義(英和)」をクリックすると、対訳資料を閲覧できます。この連載とあわせて、ぜひ原文もお読みになることをお薦めします。
箇条5は、「リーダーシップ」というタイトルで、トップマネジメントがマネジメントシステムを確立・実施・維持・改善するために発揮しなければならないリーダーシップを要求しています。
箇条5 リーダーシップ
5.1 リーダーシップ及びコミットメント
共通テキストでは、マネジメントシステムに関するリーダーシップとコミットメントを実証するために、トップマネジメントに求められる8項目が挙げられています。
1:組織の戦略的な方向性と両立するような方針、目的の確立
2:組織の事業プロセスへのXXXマネジメントシステム要求事項の統合
3:XXXマネジメントシステムに必要な資源を利用可能にすること
4:要求事項への適合の重要性の伝達
5:XXXマネジメントシステムの意図した成果の達成
6:XXXマネジメントシステムの有効性に寄与するための人々の指揮・支援
7:継続的改善の推進
8:関連する管理層がリーダーシップを発揮できるような支援
2番目に挙げられている「事業プロセスへの統合」は、新しい要求事項です。ISO/CD 14001では、「EMSを確立する際に、組織の状況に関する知識を考慮する」、「戦略計画の策定において、環境パフォーマンスを考慮する」という2項目が追加され、全部で10項目になっています。また、ISO/CD 9001では、箇条5.1.1が「QMSに関するリーダーシップ及びコミットメント」というタイトルになっていて、これら8項目に加えて、「組織内で品質方針が理解され、守られることを確実にする」、「プロセスアプローチに対する認識を高める」という項目が追加されています。さらに、箇条5.1.2が「顧客のニーズ及び期待に関するリーダーシップ及びコミットメント」というタイトルで、顧客重視に関する4項目が追加されています。
5.2 方針
組織の目的に対して適切で、XXX目的を設定する枠組みを示し、要求事項への適合と継続的改善へのコミットメントを含むようなXXX方針を確立することが求められています。さらに、XXX方針は、「文書化した情報」として利用可能で、組織内に伝達され、必要に応じて利害関係者が利用可能なものにしなければなりません。
ISO/CD 9001では、品質方針が「継続的に適切であることをレビューする」という要求事項が追加され、ISO/CD 14001では、組織のリスク及び機会に対して適切であること、汚染の予防及び環境保護に対するコミットメントなどが具体的に要求されています。また、ISO/IEC 27001:2013では、情報セキュリティ方針の中に情報セキュリティ目的を含めてもよいことになっています。
5.3 組織の役割、責任及び権限
トップマネジメントに対して、マネジメントシステムが規格要求事項に適合することを確実にするために責任・権限を割り当てること、それを組織内に伝達することを求めています。また、マネジメントシステムのパフォーマンスをトップマネジメントに報告する責任・権限を割り当てることも求めています。
ISO/CD 9001では、「トップマネジメントはQMSの有効性に対して責任をもつ」と書かれているようにトップマネジメントの責任が強調されているようです。いわゆる「管理責任者」については、要求事項にはなっていません。ISO/CD 14001の注記に「パフォーマンスの報告に関する役割及び権限は、管理責任者(複数も可)に割当てられることが多い」と書かれていますが、ISO/IEC 27001:2013にもISO/CD 9001にも「管理責任者」という表現は出てきません。“管理責任者に任せっきり”のマネジメントシステムでは、トップマネジメントがリーダーシップを発揮しているとは言えないゾということかもしれませんね。
次回は、「箇条6 リーダーシップ」について、さらっと解説します。
〜text by 研修部 萬木 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.33より〜 |
 |
 |
 |
 |
日本の2012年度「温室効果ガス排出量」速報値発表−京都議定書の目標「マイナス6%」達成見込み!−(2013.11.29) |
 |
| |
環境省は2013年11月19日、日本の2012年度「温室効果ガス総排出量(速報値)」を公表しました。2012年度の温室効果ガスの総排出量(速報値)は、13億4,100万トン(二酸化炭素換算)で、2011年度比2.5%増(3,320万トン)となっています。また、京都議定書の基準年である1990年比で6.3%増(7,980万トン)となり、第一約束期間における5ヵ年平均の総排出量は12億7,900万トン。基準年の総排出量(12億6,100万トン)を比べると、1.4%の増加となっています。
これは2008年度後半の金融危機の影響に伴い、2009年度にかけて総排出量が減少したものの、2010年度以降、景気回復及び東日本大震災を契機とした火力発電の増加により3年連続で総排出量が増加したことによるものです。
この結果、仮に森林吸収量の目標を達成し、京都メカニズムクレジットを加味すると、5ヵ年平均で基準年比8.2%減となり、京都議定書の目標(基準年比6%減)を達成する見込みとなります。なお、目標の達成状況を含む個別の対策・施策の評価・検証については、年度内に「地球温暖化対策推進本部」にて行う予定とのことです。
リーマンショックに始まり東日本大震災と原発事故問題に終わった京都議定書第一約束期間はその目標であった「マイナス6%」が達成見込みとなった一方、新たな温室効果ガス削減の枠組み作りにもようやく動きが見られました。ポーランドで開かれていた国連気候変動枠組み条約第19回締約国会議(COP19)は11月23日、2020年以降の新たな温室効果ガス排出削減の枠組み作りで、2015年3月末までの早期に各国が自主的な削減目標などを示すことに合意し、閉幕しました。
自主目標の提出期限は「準備できる参加国」という条件付きで15年第1四半期(1〜3月)までとし、15年末にはすべての国の目標が出そろうことになります。まだまだ先進国と途上国の足並みが揃っているとはいえない状況ですが、順調に進めば2015年のCOP21では、2020年以降の枠組みにおける削減目標が決定することになります。
〜text by 研修部 澤本 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.32より〜 |
 |
 |
 |
 |
OHSマネジメントシステムのISO規格化、続報!−規格番号は「ISO45001」、発行は2016年10月?−(2013.11.29) |
 |
| |
ISO規格化が決定した「労働安全衛生マネジメントシステム」についての最新情報です。10月21〜25日にかけてロンドンにおいて
ISO/PC283の第1回会合が開催されました。会合には27の加盟団体と5つのリエゾン団体から計83名の委員が出席しました。
PC283第1回会合では、要求事項開発のためのワーキンググループ1(WG1)が設立され、また規格番号として「ISO45001」が提案・了承されました(“18001”は残念ながらすでに使用されているとのことです)。
また、おおよその規格開発スケジュールが示され、開発期間を3年として2014年5月までに委員会草案(CD)、2015年2月に国際規格草案(DIS)、2016年3月に国際規格最終案(FDIS)、最終的には2016年9〜10月にIS発行とのことです。ただし、計画は今後の進展により大きく変更される可能性もあるようです。
なお、ISO/WD.1 45001(作業原案)を近々に発表するとのことで、いよいよ労働安全衛生マネジメントシステム規格開発作業がスタートします。
〜text by 研修部 澤本 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.32より〜 |
 |
 |
 |
 |
ISO9001規格の改訂動向(2013.11.29) |
 |
| |
2013年6月に発行されたCD(委員会原案)に対するコメント・投票が完了し、11月12日付けで、ステージ30.99(CDをDIS(国際規格原案)として登録)という段階に進みました。
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62085
今後、DIS(国際規格原案)、さらにFDIS(最終国際規格原案)という段階を経て、2015年の改定に向けて順調に作業が進められています。ISO9001規格は、ISO専用業務指針に収録されている附属書SLに基づいて、現在の箇条1〜箇条8までの構成から、箇条1〜箇条10の構成に大幅に変更される予定です。
〜text by 研修部 萬木 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.32より〜 |
 |
 |
 |
 |
世界のマネジメントシステム認証件数、2012年版発表(2013.11.13) |
 |
| |
世界のマネジメントシステム認証件数(ISO Survey-2012)が、ISO中央事務局より公表された。各規格の認証件数上位国は表のとおり。
|
|
ISO14001
(環境) |
ISO/TS16949
(自動車産業) |
ISO/IEC27001
(情報) |
ISO22000
(食品安全) |
ISO13485
(医療機器) |
1 |
中国
334,032件 |
中国
91,590件 |
中国
17,975件 |
日本
7,199件 |
中国
8,228件 |
ドイツ
4,140件 |
2 |
イタリア
137,390件 |
日本
27,774件 |
韓国
4,454件 |
イギリス
1,701件 |
インド
1,123件 |
アメリカ
4,074件 |
3 |
スペイン
59,418件 |
イタリア
19,705件 |
アメリカ
3,811件 |
インド
1,600件 |
ギリシャ
1,097件 |
イタリア
2,052件 |
4 |
ドイツ
51,809件 |
スペイン
19,470件 |
インド
3,793件 |
|
ルーマニア
1,011件 |
イギリス
1,573件 |
5 |
日本
50,339件 |
イギリス
15,884件 |
ドイツ
3,184件 |
ルーマニア
866件 |
|
フランス
1,129件 |
6 |
イギリス
44,670件 |
韓国
11,479件 |
日本
1,237件 |
台北
855件 |
日本
762件 |
スイス
843件 |
7 |
フランス
31,631件 |
ルーマニア
8,633件 |
ブラジル
1,180件 |
スペイン
805件 |
トルコ
741件 |
中国
765件 |
8 |
インド
29,402件 |
フランス
7,975件 |
イタリア
1,147件 |
イタリア
495件 |
ポーランド
659件 |
日本
752件 |
9 |
アメリカ
26,177件 |
ドイツ
7,034件 |
タイ
1,147件 |
ドイツ
488件 |
フランス
486件 |
イスラエル
630件 |
10 |
ブラジル
25,791件 |
アメリカ
5,699件 |
|
アメリカ
415件 |
スペイン
468件 |
台北
565件 |
なお、増加件数が多いのは、ISO9001では、1位 スペイン、2位 中国、3位 ルーマニア。ISO14001では、1位 中国、2位 スペイン、3位 イタリアとなっている。詳しくは、ISOのホームページ(http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm)をご覧ください。 |
 |
 |
 |
 |
ISO14001、改正作業がCD.2へ移行(2013.10.31) |
 |
| |
2013年10月6日〜11日に開催されたTC207/SC1/WG5ボゴタ会合において、ISO14001のCD.2(第2次委員会原案)が作成されました。当初、6月のTC207総会においてCD.2へ移行予定でしたが、CD.1へのコメント処理が終了せず、次回会合以降に持ち越されていました。今回の会合は延べ5日間という臨時WGとしては異例の長期日数を取り、残りのコメント処理を完了したとのことです。
現在、ISO/CD.2 14001は10月23日〜1月23日の3ヶ月投票に付されており、改正スケジュールも下記のようになっています。なお、スケジュールは現時点での予定であり、今後の進捗により変更される可能性があります。
・CD.2回付:2013年10月
・プリDIS:2014年2月
・DIS回付:2014年7月
・FDIS回付:2015年3月
・改正版ISO14001発行:2015年5〜6月
〜text by 研修部 澤本 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.31より〜 |
 |
 |
 |
 |
「改正省エネ法」でISO50001の活用を推奨!
−ISO50001を参考に「判断基準」見直しへ−(2013.10.31) |
 |
| |
経済産業省は、10月11日に開催された「省エネルギー・新エネルギー分科会 省工場等判断基準ワーキンググループ」において、省エネ法の「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(以下、「判断基準」)をエネルギーマネジメントシステム規格「ISO50001」を参考に見直し、来年4月施行予定の改正省エネ法に盛り込むことで一致しました。
日本はISO50001の作成段階から積極的に関与し、省エネ法との整合を図りました。しかし、具体的な措置事項についてはISO50001の方がエネルギー管理に関する事項がわかりやすく詳細に規定されていることから、小規模企業にとってはISO50001の方が受け入れやすいとの観点で今回の決定に至ったものです。「判断基準」の見直しついては以下の案があげられています。
(1)エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置の見直し
「エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置」において、「エネルギーマネジメントシステムの規格であるISO50001の活用について検討すること」という記述を追加する。
(2)適切なエネルギー管理を行うための「エネルギーの使用の合理化の基準」ア.〜カ.の取組の見直し
判断基準においては、事業者が、その設置している工場等全体を俯瞰し、適切なエネルギー管理を行うために、「1 エネルギーの使用の合理化の基準」においてア.〜カ.の取組が規定されている。これらのア.〜カ.の取組について、ISO50001に規定されている内容を参考として、明確化することが適当な事項を追加する見直しを行う。具体的には以下の<1>〜<2>に関する記述を追加する。
<1>人材や資金の確保及び配分について【新設】
ISO50001では、「4.2.1トップマネジメント」や「4.7.3マネジメントレビューからのアウトプット」において、エネルギーマネジメントシステムの実施に必要な資源の準備や配分について定めており、資源には、人的資源、専門的な技能・技術及び資金が含まれることを明示している。このため、必要な資金・人材の確保及び配分に関する記述を追加する。
<2>従業員への取組方針の周知や教育の実施について【新設】
ISO50001では、「4.3エネルギー方針」や「4.5.2力量、教育訓練及び自覚」において、従業員に対するエネルギーマネジメントに関する方針等の周知や教育の実施について定めている。このため、従業員への取組方針の周知や教育の実施に関する記述を追加する。
<3>取組方針の文書化について【カ.の修正】
ISO50001では、「4.5.4文書」において、エネルギーマネジメントに関する方針、目的、目標及び行動計画等の文書化について定めている。このため、取組方針の文書化に関する記述を追加する。
今回の改正案は、経産省令として年内に公布され、来春にも施行される予定です。
〜text by 研修部 澤本 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.31より〜 |
 |
 |
 |
 |
マネジメントシステム基礎講座/共通テキスト、逐条解説 2 (2013.10.31) |
 |
| |
「共通テキスト」は、日本規格協会の「マネジメントシステム規格の整合化動向」のwebページで公開されています。
http://www.jsa.or.jp/stdz/mngment/mngment03.asp
このページの「ISO MSS上位構造、共通テキスト及び共通用語・定義(英和)」をクリックすると、対訳資料を閲覧できます。
以下、箇条4について解説します。読みやすいようになるべく平易な表現にしていますが、理解を深めるために、ぜひ原文・邦訳もお読みになることをお薦めします。箇条4は、組織がマネジメントシステムを確立するために、組織を取り巻く内外の状況と課題とともに利害関係者のニーズと期待を把握し、マネジメントシステムを確立・実施・維持・改善することを要求しています。
箇条4 組織の状況(context)
4.1 組織及びその状況の理解
組織の目的(purpose)に関連し、なおかつ、組織のマネジメントシステムの意図した成果(outcome)を達成する能力に影響を及ぼすような、外部・内部の課題(issue)を決定(determine)することが要求されています。CD(委員会原案)9001:2013では、課題を決定する際に考慮すべき事項の具体例が示されています。また、2013年10月に発行されたISO27001:2013の注記には、ISO31000:2009(リスクマネジメント−原則及び指針)の「5.3 組織の状況の確定」を参照しています。ISO31000では、外部・内部状況とは、組織が自らの目的を達成しようとする状態を取り巻く外部・内部環境のこととされ、具体例が挙げられているので、こちらも参考になるでしょう。
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
マネジメントシステムに関連する利害関係者と、利害関係者の要求事項を決定(determine)することが要求されています。CD14001:2013では、ここで得られた知識を組織のEMSを設計する際に考慮することが求められています。また、CD9001:2013の注記には、利害関係者の例として、直接の顧客、エンドユーザー、供給者、販売者、小売業者、規制当局などが挙げられています。
4.3 XXXマネジメントシステムの適用範囲の決定
4.1で決定された内部・外部の課題と、4.2で決定された利害関係者の要求事項を考慮したうえで、マネジメントシステムの適用範囲を決定することが要求されています。さらに、適用範囲は文書化された情報として利用可能にしておくことが要求されています。CD9001:2013では、適用除外についても触れられています。
4.4 XXXマネジメントシステム
必要なプロセスとプロセスの相互関係を含めたマネジメントシステムを確立(establish)・実施(implement)・維持(maintain)・継続的改善(continually improvement)することが要求されています。CD9001:2013では、「4.4.2 プロセスアプローチ」の要求事項が追加され、QMSにプロセスアプローチを適用することが求められています。また、CD14001:2013では、ビジネスプロセスの中にEMSを統合する方法を含めて、EMSの要求事項を満たす方法について決定することが求められています。
〜text by 研修部 萬木 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.31より〜 |
 |
 |
 |
 |
マネジメントシステム基礎講座/共通テキスト、逐条解説(2013.10.1) |
 |
| |
このマネジメントシステム基礎講座で「共通テキスト」とは、ISO/IEC専用業務指針 第1部(第10版)統合版ISO補足指針(第4版)の中のAnnex SL「マネジメントシステム規格の提案」のAppendix 2「上位構造、共通の中核となる共通テキスト、共通用語及び中核と成る定義」のことを指します(長くてスミマセン)。
なお、「共通テキスト」が収録された文書である統合版ISO補足指針(第4版)は、2013年4月30日に改訂されました。旧版では、この文書のAnnex SLのAppendix 3に「共通テキスト」が収録されていましたが、現在はAppendix 2に繰り上がっています(今後も文書の改訂によって、
Annex SL、Appendix 2の位置は変わるかもしれませんのでご注意ください)。
また、「共通テキスト」は、日本規格協会の「マネジメントシステム規格の整合化動向」のwebページで公開されています。
http://www.jsa.or.jp/stdz/mngment/mngment03.asp
このページの「ISO MSS上位構造、共通テキスト及び共通用語・定義(英和)」をクリックすると、対訳資料を閲覧できます(なぜだか印刷できない設定になっています、寂しいですね)。
さて、今回の連載は箇条1から箇条10のうちの「3 用語及び定義」をさらっとご紹介します。「共通テキスト」では、ISOが発行する各マネジメントシステム規格で用いられる用語とその定義についても整合化を図るために、22個の共通の用語と定義を収録しています。
3.01組織、3.02利害関係者、3.03要求事項、3.04マネジメントシステム、3.05トップマネジメント、3.06有効性、3.06効率、3.07方針、3.08目的、3.09リスク、3.10力量、3.11文書化した情報、3.12プロセス、3.13パフォーマンス、3.14アウトソース(外部委託)、3.15監視、3.16測定、3.17監査、3.18適合、3.19不適合、3.20修正、3.21是正処置、3.22継続的改善
これらの用語の定義の内容は、ISO9000(品質マネジメントシステム−基本及び用語)、ISO14050(環境マネジメント−用語)に載っていたものとあまり変わりません(ほっ)。リスク(=不確かさの影響)、パフォーマンス(=測定可能な結果)などは、要求事項を理解する際に注意が必要な用語です。
ちなみに、用語の定義はそれぞれのマネジメントシステム規格の中に記載しても、別の文書に記載して参照してもよいことになっています。ISO9001、ISO14001のCD(委員会ドラフト)では、用語の定義はすべて規格の中に記載されていますが、9月25日に発売されたばかりの
ISO27001(発行日は10月1日)では、「ISO27000参照」となっているので、別途 ISO27000規格を購入して読まないとISO27001を正しく理解できないということになっています。さすがISOは商売上手ですね。
〜text by 研修部 萬木 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.30より〜 |
 |
 |
 |
 |
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書、第1作業部会報告書が公表されました(2013.10.1) |
 |
| |
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書第1作業部会報告書(自然科学的根拠)が公表されました。本報告書は、2007年の第4次評価報告書以来6年ぶりとなるもので、この間に出された新たな研究成果に基づく地球温暖化に関する自然科学的根拠の最新の知見がとりまとめられています。今後本報告書は「気候変動に関する国際連合枠組条約」をはじめとする、地球温暖化対策のための様々な議論に科学的根拠を与える重要な資料となります。本報告書の主要な結論は以下のとおりです。
【観測事実】
気候システムの温暖化については疑う余地がない。1880〜2012年において、世界平均地上気温は0.85[0.65〜1.06]℃上昇しており、最近30年の各10年間の世界平均地上気温は、1850年以降のどの10年間よりも高温である。
世界平均地上気温は数十年にわたって明確な温暖化を示しているが、その中には、概ね十年程度の周期での変動や年々の変動もかなり含まれている。過去15年(1998〜2012年)の世界平均地上気温の上昇率は1951〜2012年の上昇率より小さい。
1971〜2010年において、海洋の上部(0〜700m)で水温が上昇していることはほぼ確実である。
1992〜2005年において、3000m以深の海洋深層で水温が上昇している可能性が高い(新見解)。
海洋の温暖化は、気候システムに蓄えられたエネルギーの変化の大部分を占め、1971〜2010年の期間ではその90%以上を占めている(高い確信度)。
過去20年にわたり、グリーンランド及び南極の氷床の質量は減少しており、氷河はほぼ世界中で縮小し続けている。また、北極の海氷面積及び北半球の春季の積雪面積は減少し続けている(高い確信度)。
19世紀中頃以降の海面水位の上昇率は、それ以前の2千年間の平均的な上昇率より大きかった(高い確信度、新見解)。
【温暖化の要因】
人間活動が20世紀半ば以降に観測された温暖化の主な要因であった可能性が極めて高い。
1750年以降の二酸化炭素の大気中濃度の増加は、地球のエネルギー収支の不均衡に最も大きく寄与している。太陽放射は20世紀にわたるエネルギー収支の不均衡にほとんど寄与していない。
【将来予測】
1986〜2005年を基準とした、2016〜2035年の世界平均地上気温の変化は、0.3〜0.7℃の間である可能性が高い(確信度が中程度)。
世界平均地上気温の上昇に伴って、ほとんどの陸上で極端な高温の頻度が増加することはほぼ確実である。中緯度の大陸のほとんどと湿潤な熱帯域において、今世紀末までに極端な降水がより強く、頻繁となる可能性が非常に高い。
二酸化炭素の累積排出量と世界平均地上気温の上昇量は、ほぼ比例関係にある(新見解)。
気候変動は陸地と海洋の炭素吸収を一部相殺してしまうことの確信度は高い。この結果、排出された二酸化炭素は、大気中により多く残ることになる。
海洋へのさらなる炭素蓄積の結果、海洋酸性化が進行するであろう。
なお、今回承認された第1作業部会報告書については、10月中に気象庁ホームページにおいて日本語訳を公開する予定です。また、報告書各章の概要等については、IPCCから公表された後、同じく気象庁ホームページにおいて日本語訳を公開する予定です。
〜text by 研修部 澤本 メールマガジン 「グローバル・ニュース」 Vol.30より〜
|
 |
 |
 |
 |
バックナンバーはこちら |
 |
 |
 |